みなさん、こんにちは!Pendemyのコラムへようこそ🐧
第5回目のテーマは、STEAM教育の観点から見た習い事選びについて。
子どもの未来につながる習い事のポイントについてお伝えします!
はじめに:「この習い事でよかったのかな?」と迷うすべての保護者へ
子どもの習い事、どうやって決めていますか?
「周りの子がやっているから」「本人がやりたいと言ったから」「将来のために役立ちそうだから」
——どれもよくある理由ですし、間違っているわけではありません。
でも、習い始めてしばらくすると、こんなふうに感じることはありませんか?
「本当にこの習い事でよかったのかな…?」
せっかく時間とお金をかけて続けているのに、子どもがなんとなく飽きていたり、やる気が見えなかったりすると、親としても悩みますよね。
そんなときに、ひとつの「ものさし」になるのが「STEAM教育の視点」です。
習い事選びの判断軸としてこの考え方を知っていると、今だけでなく、将来の学びや生き方にもつながる選択ができるようになります。

そもそもSTEAM教育ってなに?
最近よく耳にする「STEAM教育」。
でも、「理系っぽくてうちの子には関係ないかも」と思っていませんか?
実はそれ、ちょっともったいない誤解かもしれません。
STEAMとは、次の5つの分野の頭文字をとった言葉です。
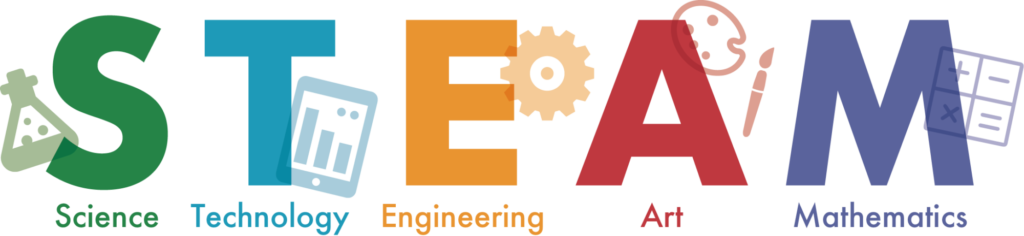
• S:Science(科学)
• T:Technology(技術)
• E:Engineering(工学)
• A:Art(芸術・表現)
• M:Mathematics(数学)
これらをただ学ぶだけではなく、
「つなげて考える」「自分なりの答えを見つける」力を育てていくのが、STEAM教育の特徴です。
たとえば、ロボットを動かすには、技術や数学だけでなく、
「何を」「どんな順番で」ロボットへ伝えればいいかを、筋道を立てて考えることが大切です。
つまり、ロボットプログラミングを通して学べるのは、理系の知識だけでなく、考える力や伝える力も含まれているのです。
「これからの社会で必要な力」と言われる、
• 問題を見つけて考える力
• チームで協力する力
• 正解がない中でもチャレンジする力
そうした力を、遊びのような体験の中で育てていく。それがSTEAM教育です。

習い事選びにSTEAM視点が必要な理由
学校ではなかなかできない体験があるから
学校の授業では、「教科ごと」に分かれて学びます。国語は国語、算数は算数。
でも、実際の社会では、いろんな知識やスキルを組み合わせて考えることが当たり前です。
STEAMの視点をもった習い事は、そうした「教科の壁をこえて考える力」を育ててくれます。
失敗から学ぶ“本物の体験”があるから
多くの習い事では、「正しい答え」「上手にできること」を目指します。
でもSTEAM的な習い事では、「失敗したらやり直せばいい」「どうすればうまくいくかを試す」ことを大事にします。
それが、粘り強さや試行錯誤する力につながるのです。
「好き」が「得意」に変わるチャンスがあるから
子どもは、自分が興味をもって取り組めることなら、どんどん吸収します。
STEAMの視点をもった習い事は、「やらされる」のではなく「やってみたい!」という気持ちを引き出す工夫がたくさんあります。
その「好き」の芽が、将来の「得意」や「自信」に変わっていくのです。

STEAM的な学びがある習い事の見つけ方
では、具体的にどんなポイントを見て選べば、STEAM教育の視点がある習い事に出会えるのでしょうか?
体験の前や見学のときにチェックしたい3つの視点をご紹介します。
「結果」より「プロセス」を大切にしているか?
作品の完成度よりも、「どう考えて作ったか」を大切にしてくれる習い事は、子どもの考える力を伸ばします。
「答えがひとつじゃない活動」があるか?
「こうしなさい」と型を教えるだけではなく、自分で選んで決める体験があると、創造性が育ちます。
子どもの「なぜ?」「やってみたい!」を起点にしているか?
子どもの疑問や発想を大事にする教室は、自然とやる気を引き出してくれます。

【事例紹介】具体的にどんな習い事がある?
STEAM的な学びができる習い事と聞いて、まず思い浮かぶのは「プログラミング」や「ロボット」かもしれません。
実際、それらはSTEAMの要素がぎゅっと詰まった代表例です。ですが、それだけではありません。ここでは、ジャンル別にいくつかの例を紹介します。
プログラミング・ロボット・デジタル系(王道)
コンピュータを使って指示を出し、ロボットやキャラクターを動かす活動は、論理的思考や試行錯誤の力が自然と身につきます。
特に、「ただ動かす」のではなく「目的を自分で考える」ような課題がある教室なら、より深い学びが期待できます。
たとえば、私たちPendemyが運営するロボットプログラミング教室では、ただプログラムを学ぶのではなく、「なぜその動きをさせるのか?」といった問いを大事にしながら授業を進め、3ヶ月に1回学んだ内容を活かしたオリジナルロボット制作・発表の授業を設けています。
発表やリフレクションの時間もあり、子どもたちは「伝える力」や「他の子の考えを聞く力」も育んでいます。

理科実験・ものづくり・アートなど(広がる選択肢)
STEAM教育の特徴は、「どれか一つの教科にとらわれないこと」。
たとえば、アートや音楽も、問いかけと探究を伴えば、立派なSTEAM活動になります。
PendemyのSTEAM工作教室では、「こう作ってください」ではなく、子ども自身がアイデアを出しながら作品をつくる自由工作スタイルが中心です。
素材の選び方や、作り方、完成後の使い方まですべて自由。子どもたちは何度も試行錯誤しながら、自分だけの作品を生み出しています。
たとえば…
- 自身の作りたいものを、iPadでモデリング、3Dプリンターで印刷し色塗り、装飾を行う
- 水車や風車を作り、どうやったら早く回るのかを実験しながら改良
- 実験+表現をかけあわせた“スライムアート” など
「自分で考える」「つくって試す」といった体験の中で、STEAM的な力はぐんぐん育ちます。

探究型教室・自由研究型の習い事(注目ジャンル)
最近は、「自分の興味を起点に、テーマを決めて学ぶ」教室も注目されています。
こうした教室では、先生は答えを教えるのではなく、子どもの問いに寄り添い、必要な知識や視点を一緒に探していく“伴走者”のような存在です。
たとえば…
◾ 探究学舎(東京都三鷹市/オンライン)
「感動から始まる学び」をコンセプトに、理系・文系・芸術などジャンルを問わず、子どもたちが“物語の主人公”のようにテーマにのめり込めるプログラムを展開しています。
宇宙・遺伝子・哲学・数学など、学問を「冒険」に変える独自の切り口が特長です。
◾ 進研ゼミ・チャレンジスクール「オンラインたんきゅう」講座(ベネッセ)
ベネッセが提供する「チャレンジスクール オンラインたんきゅう講座」は、身の回りの「なぜ?」から出発し、子どもたちが自分の考えを深めていく探究型のオンライン講座です。
テーマは「宇宙」「自然」「未来の仕事」「歴史のひみつ」など多岐にわたり、
- 動画やワークで知識を得て、
- 自分の考えを言葉にまとめ、
- 講師や他の子どもと共有・対話する
という一連の流れを通して、思考力・表現力・好奇心を育てていくことが特徴です。
失敗しないためのチェックリスト
「いろいろな習い事があるけれど、うちの子に合っているのはどれだろう?」
「STEAM教育って、なんとなくよさそうだけど、実際どう選べばいいの?」
そんなときに役立つのが、以下の7つの視点です。
◆ 習い事選びの7つのポイント
- 子どもがワクワクしているか?
→体験の時点で「やってみたい!」という気持ちがあるかどうかは、とても大事なサインです。 - 正解がひとつじゃない活動があるか?
→「こうしなきゃいけない」ではなく、「自分で考えてみる」がある教室を選びましょう。 - 失敗しても笑える雰囲気があるか?
→失敗を否定せず、「どうすればよかった?」と一緒に考える空気があると、挑戦を続けられます。 - 先生が子どもに問いかけてくれるか?
→答えを教えるのではなく、「どう思う?」「どうしたい?」と聞いてくれる先生は、STEAM的学びのパートナーです。 - 完成よりも“考えたこと”をほめてくれるか?
→うまくできたかどうかより、「こんな工夫をしたね」と声をかけてもらえると、自信につながります。 - 子どもが「もう一回やりたい」と言うか?
→続けたいかどうかは、習い事が「自分の学び」になっているかのバロメーターです。 - 家庭でも話題になるような学びがあるか?
→「今日こんなことしたよ!」と子どもから話してくれるような習い事は、心を動かす体験が詰まっています。
このチェックリストは、Pendemyの教室でも大切にしている視点です。
体験の後にお子さんが「また行きたい!」「今日はこれができたよ!」と目を輝かせて話してくれるなら、それはもう、その習い事が“育ちの場”になっている証拠かもしれません。
まとめ:子どもの“未来力”を育てる習い事を
習い事選びは、子どもの人生を左右するような大きな選択にも感じられます。
でも、完璧な答えを求めるよりも、「どんな成長を大切にしたいか」という軸を持つことが何より大切です。
STEAM教育の視点は、
• 子どもが考える力を育てる
• 失敗を怖がらずにチャレンジできる
• 「好き」が育つ体験になる
そんな視点を親として持っていることで、習い事は“時間つぶし”でも“スキルの先取り”でもなく、「未来につながる学びの場」に変わります。
あなたのお子さんにぴったりの、“育ちを応援する習い事”が見つかりますように。

